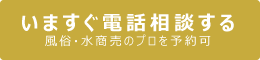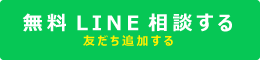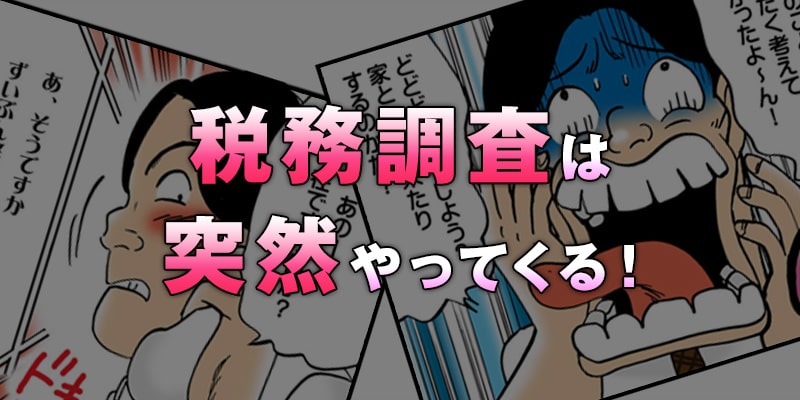キャバクラやホストクラブ、ラウンジなどで水商売といわれる夜職で働いている人の中には、自分で確定申告を行う必要がある人もいることをご存じでしょうか。どのようなケースに該当する場合、確定申告が必要になるのでしょうか。
今回は、夜職で働いている人の中で確定申告が必要な人と確定申告を行わなかった場合のリスク、確定申告を行うことによって得られるメリットについてご紹介します。
これから確定申告が必要な方は税理士法人松本までお気軽にご相談ください。
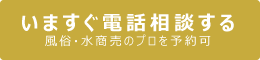
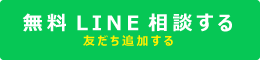
夜職で確定申告が必要な人と不要な人の違いとは
夜職の仕事に就いている人の中でも、確定申告をする必要がある人と確定申告の必要がない人がいます。確定申告の必要がない人とは、勤務先のキャバクラやホストクラブ、ラウンジなどと雇用契約を結び、お店の従業員として働いている人です。お店の従業員として働いている場合は、お店側が源泉所得税を給与から天引きして納税し、年末調整も行っているため、個人として確定申告を行う必要はありません。
一方、お店と雇用契約を結ばずに水商売の仕事をしている人は、確定申告を個人で行う必要があります。
お店と雇用契約を結んでいない人は、確定申告が必要
確定申告とは、1月から12月までの1年間に得た所得を申告し、所得に応じて定められた税金を支払う行為のことです。お店の従業員として働いている夜職の人は、店側が1年間に支払った給与の額を計算し、年末調整を行っています。そのため、個人が所得額を申告する確定申告を行う必要がないのです。
しかし、お店と雇用契約を結んでいない人の場合は、店側が1年間の所得について申告を行っていないため、自分で確定申告を行い1年間で得た所得について申告を行わなければならないのです。確定申告が必要になるケースは1年間に48万円以上の所得を得た場合となります。
また、お店と雇用契約を結んでいない方には以下の2つのケースがあります。
源泉徴収されている場合
お店と雇用契約は結んでいない場合でも、お店からもらう報酬からは税金が引かれているという方もいらっしゃるでしょう。報酬から税金が引かれている(源泉徴収されている)場合は、店側が代わりに納税をしています。しかしながら、納税は行われていても一年間の所得については申告がなされていないため、自分で確定申告をする必要があります。所得税に関しては店側から納税されていますが、お店から発行される支払調書や報酬明細や経費書類をもとに確定申告を行いましょう。
所得が極端に多くなければ確定申告後に納めすぎた分の所得税が還付される可能性が高いです。
源泉徴収されていない場合
お店から支払われている報酬から所得税が引かれていない場合は、お店が税金を納めていないことになります。そのため、確定申告によって所得を申告し、所得額に応じた所得税を納付しなければなりません。
副業として夜職の仕事をしている人
最近では本業を別に持ち、副業としてキャバクラやホストクラブ、スナックなどの夜職で働いている方も増えています。本業で得た給与に関しては、会社側が年末調整を行っているため個人が確定申告をする必要はありません。しかし、副業としての所得がある場合、副業で得た所得についての確定申告が必要なケースと不要なケースがあります。
夜職の副業で確定申告が必要なケース
副業としての所得が20万円を超えた場合には、副業の所得について確定申告を行う必要があります。
夜職の副業で確定申告が不要なケース
副業としての所得が20万円以下であった場合には、副業の所得について確定申告を行う必要はありません。
ただし、住民税の申告は必要になりますので、覚えてきましょう。
夜職で働く人が確定申告を行うメリットとは
確定申告と聞くと、何となく難しそうなイメージや手間がかかりそうなイメージがあり、手続きに躊躇してしまう方もいるかもしれません。しかし、夜職で働く方は確定申告によってメリットを得られる可能性もあるのです。
確定申告を行う前に、まずは相談してみたいという方は税理士法人松本までお気軽にご相談ください。
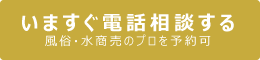
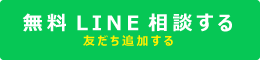
税金が還付される可能性がある
所得税は、1年間の所得によって課税額が変わります。お店から支払われる報酬から所得税が源泉徴収されている場合、毎月10.21%が所得税として天引きされていると思います。しかし、年間の所得金額が確定した時に、本来納めるべき税金よりも多く支払い過ぎているケースがあります。そのような場合に確定申告を行うと、払いすぎていた税金が返金(還付)されるようになります。
経費として計上できる費用がある
確定申告では、仕事に必要な出費を経費として計上することができます。水商売の場合は、以下のような出費が経費として認められています。
・仕事用の衣装代
・ヘアメイク代
・仕事専用に使っている携帯電話の料金
・仕事帰りに公共交通機関がない場合のタクシー代
経費として計上できる金額は収入から差し引くことができるため、所得額が下がり、所得税も少なくなる可能性があります。
確定申告のデメリットとは
確定申告は、一定の所得を得ている人であれば行わなければならない手続きです。しかしながら、確定申告を行うためには確定申告書を作成するという手間がかかります。国税庁のサイトには、確定申告書作成コーナーが用意されており、インターネットを利用してパソコンやスマートフォンでも書類を作成することができます。確定申告に慣れている人であれば、戸惑うことなく書類を作成できる可能性もありますが、初めての確定申告の場合などは、どこまで経費が認められるのか、判断に迷うケースも出てくるでしょう。
確定申告に不安を感じているようであれば、税理士に相談することをお勧めします。経費として計上できる支出についてのアドバイスを受けることもできるため、節税につながる可能性もあります。
確定申告を行わなかった場合のリスクとは
確定申告は、一定の所得を得た法人や個人が1年間の所得を申告し、納税を行う手続きです。日本国憲法において納税は国民の義務と定められており、正しく所得を申告して納税を行わなかった場合には無申告という扱いになります。無申告の場合、ペナルティとして無申告加算税や延滞税が追徴課税されることとなります。
また、意図的に申告を行わなかった場合など悪質性が高く、無申告の金額が大きい場合には、脱税の罪で刑事裁判に発展するケースもあります。確定申告が必要なケースに該当する場合は、必ず確定申告を行うようにしましょう。
まとめ
キャバクラやホストクラブ、ラウンジなど夜職のお店で働く人の中には、確定申告が必要な人、確定申告が不要な人がいます。ご自身が確定申告の必要な人に該当している場合、無申告のままでいると、より多くの税金の納付が必要になり、場合によっては刑事告発されるなどのリスクが生じます。
確定申告が必要なケースに当てはまっているようであれば、必ず確定申告を行うようにしましょう。確定申告について不安を感じている場合は、まず税理士に相談することをおすすめします。